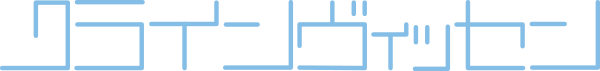- トップページ |
- 新着情報・コラム
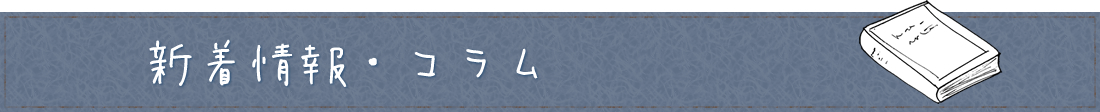
ヴィッセン出版の新着情報やコラムをご紹介致します。
歩き回る編集者 1回め
2022年05月22日畑作地歩き

しょっちゅう遠出をするわけでもないが、毎日の散歩で2時間ほど周辺を歩く。編集部がある周辺は一面の畑作地で、2020年2月に日本農業遺産に認定された干し野菜の産地である。11月になると巨大な干しやぐらが建てられ、大根を干す。1月、年が開ける頃まで寒風にさらし、すっかり水分が抜けた大根は、千切り大根やたくあんに加工され、全国へと出荷される。
この一帯の畑には鰐塚山からの冷たい風がおりてくるので、干し野菜づくりには適しているそうだ。

でも日本農業遺産に認定されたのは、ただ干し野菜の産地だからではない。近代農耕地域にはめずらしく、耕畜連携によって土作りから、生物多様性の維持から、農薬・化学肥料の制限から、すべてがうまく回る仕組みができていることによる認定だと聞いた。
この地域は畑で作物を育てている傍らで、畜産が営まれている。畑のそばに牛舎がある。住宅地のなかにも牛舎がある。散歩の途中で牛の声が間近で聞こえる。そういう地域なのである。
こうした環境を生かして、畑での同作物連作を避けるための牧草が育てられている。牧草を刈り取ったあとは、土に牧草の根をすきこみ、滋養豊かな土をつくる。また、牛たちのフンは堆肥となり畑の土を改良するために使われる。
滋養豊かな土は健康な野菜を作るのに欠かせない。野菜が健康に育ちやすい土地だから、必要以上に病害虫を抑えるための農薬を散布する必要もなく、多くの昆虫が生息する環境を維持できる。そのことは天敵昆虫となるものもたくさん生息していることを意味し、さらに農薬による駆除を必要としなくなるということにもなる。
さらにいえば、昆虫がたくさん生息する環境には、多くの鳥類が暮らすことができる。スズメ、ムクドリ、モズ、チョウゲンボウ、カラス、トビなどは馴染みの鳥たちである。
このように農薬や化学肥料を使わずとも生産性が高められるシステム(エコシステム)が構築されるのである。
じつは、毎日の散歩で、あぜ道や休耕畑に雑草が生い茂っている景色をみて、「ほったらかしだな」と思っていたのだが、これにも意味があったのだ。
あぜ道や休耕畑に雑草を生い茂らせておけば、そこで昆虫たちの暮らしがなりたち、生産物への虫害が抑えることができるわけだ。
じつによく考えられた農耕システムであることか。
編集部の脇にある庭に箱庭板農耕システムを造ってみたくなった。まずはトンボなどの捕虫昆虫を呼べるビオトープをつくり、家庭菜園をつくり、鳥たちが来るように木を植えよう。

そして、3年目。箱庭版農耕システムはギクシャクしながら周りだし、庭ではモズの夫婦が餌場として顔を見せるようになり、昆虫を食べにムクドリが集まり、それを高みから狙っているチョウゲンボウが姿を見せるようになった。
家庭菜園の収穫はアスパラ、キャベツなど、夕餉を賑わすとまでは行かないが、楽しみを添えてくれている。

今年は蜂の巣(うと)を2つ設置した。ミツバチが入ってくれると、うれしい。
Copyright©2009-2016 Wissen. All Rights Reserved.